全ての主語は 「子どもたち」
子どもたちを起点にした
学校デザイン
「子どもたちを信じる」その出発点に立った時にどんな学校ができるんだろう?
そんな問いから私たちの新たな学校デザインは始まりました。
「未来の学校はこんな姿です!」と社会に示せるように、みんなでつくり続けています。
月曜日に行きたくなる学校
月曜日に行きたくなる学校
こんな学校あったらいいな
子どもたちにとって、学校は月曜日になったら行きたくなるような場所であってほしい。
どの子にとっても心理的な安全性があり、自己肯定感を感じられる場であってほしい。
学校が子どもたちの「居場所」になることが、学びや成長の第一歩です。
空間づくりはもちろん、先生や子どもを含めた温かい人間関係づくりも大切にしています。
日本中の学校が「月曜日に行きたくなる」ように、私たちは先頭に立って進化を続けていきます。
子ども主体の学校運営
誰もがつくり手
子どもたち、保護者、先生、関わるみんなが学校のつくり手です。
日々の運営、ルール作り、行事、授業などをみんなでつくっていっています。
うまくいくこともありますが、みんなでつくることを繰り返していけば「自分で社会を変えられる」と思ってくれる人が育つと考えています。
全校ミーティング

全校ミーティング
小学校の「全校ミーティング」では、学校のルールの中で、見直していきたいものが提案され、話し合い、必要に応じて刷新していきます。
話し合いは子どもたち主導で進められますが、保護者、先生、学園、など必要なステークホルダーの意見も子どもたちが聞きながら合意形成していきます。
休み時間をのばしたい、筆箱の中身を考えたい、毎朝体操着に着替える必要があるの?、校内にリラックススペースをつくりたい、など多くのテーマが取り扱われ、実際にルールをアップデートしながら、子どもたちが主体的に学校運営を行う仕組みです。
行事
行事をつくることは、企画・調査・準備・役割分担・臨機応変な対応など子どもたちにとって大きな成長の要素があります。
この成長の機会を、「効率化」のために大人が奪ってしまうことは非常に勿体ないことだと思います。
子ども園の卒園遠足、小学校のスポーツデイ、中高のスタディツアーをはじめ各種行事を子どもと大人でつくり、最後にみんなの笑顔が見られることで、大きな成長と満足感があります。
学習者中心の学び
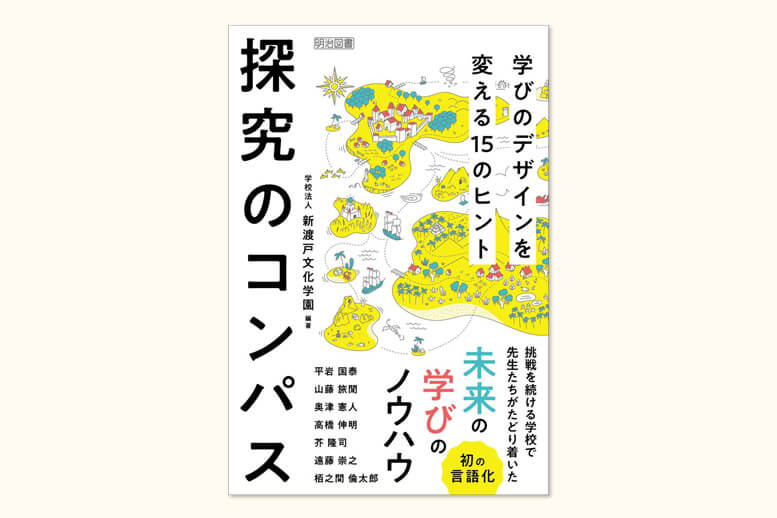
学習者中心の学び
あなたの学びは、あなたが決める
この言葉は、私たちが2025年に出版した書籍「探究のコンパス」第1章のタイトルです。
「学びの舵を握るのは学び手本人である」という基本思想が私たちにはあります。
初代校長の新渡戸稲造博士は「教職員心得」に「学課を授くるに智育のみに偏せざるよう思慮と判断力の養成に努むること」と書いていました。学園創立以来、大人が知識を詰め込むだけではなく、子どもたち自身が考え、学び続ける姿を求めて教育活動を展開してきました。
受験が終わった途端に勉強しなくなる教育ではなく、生涯学び続ける学習者が育つことを目指して、新渡戸文化学園の学びが幼児から学生までにわたり展開されています。
日本財団アンケート(※)と新渡戸文化中学校・高等学校の回答値比較

自分は責任ある社会の一員だと思う

将来の夢を持っている

自分で国や社会を変えられると思う

社会問題について、家族や友人など周りの人と積極的に議論している
(※)日本財団「18歳意識調査」第20回 テーマ:「国や社会に対する意識」



